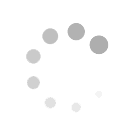注意事項
商品所在地距離海外收貨處(神奈川)較遠,請注意日本運費
google翻譯
google 翻譯僅供參考,詳細問題說明請使用商品問與答
1985年の低俗コメディの極致:『トンボーイ』——ジェンダーの境界を嘲笑うか、挑戦するのか?
1985年、レーガン政権下のアメリカで、ポップカルチャーは過剰な明るさと無責任な享楽主義に満ちていた。MTVの台頭、ビデオテープの普及、そしてハリウッドのB級映画ブームが交錯する時代に、Herb Freed監督の『トンボーイ』(原題:Tomboy)は、ひっそりと劇場に滑り込んだ。低予算のCrown International Pictures制作で、予算わずか200万ドルながら興行収入1400万ドルを叩き出したこの作品は、表向きは「少女が少年のふりをしてレーシングの世界に挑む」ジェンダー・クロッシングの物語を掲げつつ、実態は80年代特有のセックス・コメディのテンプレートをなぞっただけの陳腐なエンターテイメントだ。主演のBetsy Russellが演じる主人公Tommyは、宇宙飛行士の父を持ちながら、自身はガレージで車をいじくり回す「トンボーイ」——つまり、男勝りの少女として描かれる。彼女の恋の相手は、レーサーRandy Starr(Gerard Christopher)で、典型的なマチズモ男としてTommyの挑戦を嘲笑う。物語は、TommyがRandyのレーシングチームに潜入し、性別を隠して活躍するコメディに発展するが、そこに散りばめられたヌードシーンや下品なジョークが、作品の野心を即座に台無しにする。
批評家たちの反応は、予想通り冷ややかだ。Rotten TomatoesのTomatometerはわずか33%と低迷し、わずか3つの批評レビューしか集まっていない。 その中でも、David NusairのReel Film Reviewsは容赦ない。「80年代の馬鹿げたセックス・コメディは数多かったが、『トンボーイ』は間違いなくそのジャンルのどん底を記録する」と断じ、0/4の惨憺たる評価を下している。 確かに、この映画は「Tootsie」(1982年)のようなクロスドレッシングの風刺を借りつつ、深みゼロの浅薄さを晒す。Tommyの「男装」は、単なるヌード露出の口実に過ぎず、ジェンダーの流動性を探求するどころか、女性の身体を消費する道具としてしか機能しない。Austin Chronicleの批評家は、これを「露骨な獣性ショットや股間ショットを毎度毎度挿入し、女性の自己表現を支持するふりをしつつ、結局は『いいケツさえあれば何でもいい』という考えで台無しにしている」と痛烈に批判する。 彼の指摘通り、Tommyの「トンボーイ」ぶりは、バスケットボールで汗を流すシーンやバイクを飛ばすアクションで強調されるが、すぐにシャワー室でのヌードや、ドーナツドレスを着た友人Sevilleのコメディ・リリーフに取って代わられる。こうした構造は、フェミニズムのポーズを張りながら、視聴者の視線を女性の肉体に釘付けにする、典型的な80年代の二枚舌だ。
それでも、『トンボーイ』を単なるゴミクズとして葬り去るのは早計かもしれない。Mutant ReviewersのJustinは、この作品を「深いフェミニスト声明ではないが、ステレオタイプを崩す試みは見られる」と擁護する。 Tommyは、確かに「男の世界」を侵食する存在として描かれる。彼女の父はNASAの宇宙飛行士で、Tommy自身も溶接やエンジンチューニングに長け、レーシングカーに「ハイテク」改装を施す——1985年の文脈では、コンピューターをくっつければ何でも未来志向になるという、痛快なナイーブさが漂う。Randyのミソジニー(女性嫌悪)は、物語の序盤で強調され、「女がレースに出るなんて!」と吐き捨てる彼の台詞は、Tommyの成長を促す触媒となる。クライマックスのレースシーンでは、Tommyの車がアフターバーナーのようなブースターで爆走し、観客を沸かせる。Justinはこれを「ガールパワーのオフキルなテーマ」と評し、脚本の弱さを認めつつ、「奇妙な瞬間や台詞(指をしゃぶるシーンとか?)が、極端な凡庸さを防いでいる」と指摘する。 確かに、映画の魅力はこうした「奇抜さ」に宿る。Sevilleのドーナツドレス姿でのミュージックビデオ風の挿入歌、またはパーティーシーンでのボクシング風前戯——これらは、Herb Freedの監督ぶりが低予算ゆえの即興性を発揮した産物だ。Freedは、こうしたB級映画の帝王として知られ、『スーパーチキン』(1982年)のようなカルト作を手がけているが、『トンボーイ』ではそのセンスが冴え渡る一方で、脚本の平板さが足を引っ張る。プロットの予測可能性は、Letterboxdのユーザーrowdyburnsが嘆くように、「前提を届ける気がない」。 Tommyの男装が即座にバレる設定は、伝統的な「隠し事の暴露」を避け、むしろ「美しい女性がトンボーイとして認められる」プロセスを描くが、そこに深掘りがないため、ただのエロティック・ファンタジーとして矮小化される。
演技面では、Betsy Russellの存在が最大の救いだ。Russellは、後の『プライベート・スクール』(1983年)でのヌードシーンで注目されたが、『トンボーイ』ではそのイメージを逆手に取り、Tommyの「男勝り」さを魅力的に体現する。Brian OrndorfはBlu-ray.comで、「Tommyは一面的で完全に非合理的だが、Russellはそれを容易く捉え、作品の焦点として義務を果たす」と絶賛、B-の評価を与える。 Letterboxdのceluloidも、「Betsy RussellはPhoebe CatesやMichelle Pfeifferに比べて過小評価されている。性的政治は陳腐だが、ノスタルジックな魅力がある」と語る。 RussellのTommyは、ライダースジャケットを羽織り、汗だくで車を修理する姿で、80年代の「強い女性像」を予感させる。彼女の視線は鋭く、Randyとのラブヘイト関係では、単なるヒロインではなく、積極的なセクシャリティを主張する。一方、Gerard ChristopherのRandyは、ステレオタイプのマチズモを演じきるが、深みに欠ける。Kristi SomersのSevilleは、ドーナツのコマーシャルオーディションで失敗を繰り返すコミック・リリーフとして機能し、captainmcclutchは「TommyとChesterの可愛い関係性」を褒めるが、全体の演技水準は低い。 Austin ChronicleはRussellを「耐えがたい」と酷評するが、これは過剰だ。むしろ、彼女の魅力がなければ、この映画はただのスラップスティック・コメディの残骸に過ぎなかっただろう。
ユーモアの観点から見ると、『トンボーイ』は80年代の「ラフでカジュアルなヌード」の象徴だ。Justinは、「現代のヌードは常に性的文脈だが、80年代はただの日常シーンで服を脱ぐだけ」と指摘し、シャワー室の男女混合や湖畔のシーンを「ランダムなヌードの連発」と揶揄する。 maxari4のLetterboxdレビューは、「性的政治は最悪だが、それがいっぱい詰まっている!」と皮肉る。 これらの要素は、セクシズムの極みとして非難されるが、同時にカルト的な魅力を生む。YouTubeのレビュー動画でも、「史上最もセクシーな映画」と揶揄され、視聴者を「ウィンスと笑いの狭間」に置く。ユーモアは、モンタージュの多用(スローモーションのレーシングやデートシーン)に頼り、ポップソングのBGMが安っぽいノスタルジーを喚起する。jasongannonは「20分でギブアップ。Hardbodies(1984年)でさえキューブリック級」と吐き捨てるが、これは過言。 実際、こうした低俗さが、今日の「So-bad-it's-good」文化で再評価されている。
文化的影響を考えると、『トンボーイ』は80年代B級映画の鏡像だ。フェミニズムの波が訪れつつあった時代に、「It's not just a man's world anymore!」というポスターのスローガンは、表層的なエンパワーメントを謳うが、内容は逆行する。Mutant ReviewersのJustinは、「ガールパワーの試みはあるが、バランスが悪い」と総括し、興行成功を「低予算の勝利」と認める。 Letterboxdのユーザーたちは、nostalgiaを武器に擁護——Paul Charmanはバナナのシーンでレビューを放棄するほど混乱し、celuloidは「30年以上経って、幼少の記憶を癒す」と回顧する。 今日、ストリーミング時代に蘇るこの映画は、#MeToo後の視点で再解釈されうる。Tommyの挑戦は、ジェンダーの境界を曖昧にするが、ヌードの乱用は女性の客体化を露呈する。OzのeFilmCritic.comレビューは2/5と中庸だが、こうした二面性が作品の耐久性を与える。
結論として、『トンボーイ』は傑作ではない。脚本の凡庸さ、演技の粗さ、セクシズムの氾濫が、Herb Freedの野心を葬る。だが、Betsy Russellの輝きと、80年代の無垢な馬鹿げたさが、忘れがたい余韻を残す。批評家たちの辛辣な言葉——Nusairの「どん底」、Austin Chronicleの「避けるべき」——は正鵠を射るが、Justinの「奇妙さが救う」という洞察が、カルト映画としての可能性を示唆する。 もしあなたが、レーガン時代の残り香を嗅ぎたいなら、このトンボーイに賭けてみよ。きっと、指をしゃぶりたくなるほどの奇妙さに、出会うだろう。
(2025年 11月 2日 21時 39分 追加) OPPAIUNKO >